
こんにちは。いつもお読み頂きありがとうございます。
今回はアニメプロデューサーであり実業家でもある竹内宏彰(たけうち ひろあき)さんから聞いた話の中から、【ハロウィンはイノベーションでありクリスマスはマーケティングである】という話をご紹介します。竹内さんは非常に多くのことを手がけていますが、「君の名は。」で一躍有名になった新海誠監督を見出し「ほしのこえ」や「秒速5センチメートル」を発表したこと特に有名ではないでしょうか。
さて、表題の件は「イノベーションの意味は?」「イノベーションの反対は何かわかるか?」といった竹内さんの話の中で出てきた例え話ですが、こういう着眼点や発想は大切だなと感じたのでご紹介します。
また、これと合わせてハロウィンとクリスマスそのものについても掘り下げます。
イノベーションの反対はマーケティングである
まず、表題の【ハロウィンはイノベーション、クリスマスはマーケティング】は、竹内さんによる「今の日本がイケてない理由」という話の流れで出てきました。
「今までの日本はマーケティングが上手く言っていたから成功していた。しかし今、そしてこれからの時代で求められるのはイノベーション。ここが足りない」という話になり、
- 「イノベーションってどういう意味?」
- 「じゃあイノベーションの逆は?」
という質問に対する答えの例えとして取り上げられました。
順を追って解説していきます。
マーケティングとは「過去を調査するもの」
マーケティング自体については カテゴリー:マーケティング で歴史や調査方法を紹介していますが、竹内さんいわく、「マーケティングというのは消費者の需要や市場を調査・分析をし、そこに変化や違いといった差別化を図ることで結果を出していくもの。
つまり「マーケティングは過去に対して行うもの」ということでした。
イノベーションとは「未来を作るもの」
一方のイノベーションは「はじめて」「今までなかった」モノ(商品)やサービスを生み出し、既存の市場や社会の仕組みに変化を起こす。
つまり「イノベーションは未来に対して行うもの。未来を作るもの」ということでした。
※イノベーションについては以下の記事でも触れていますので、合わせてご覧ください。
これらを踏まえて「イノベーションの反対はマーケティングである」というわけです。
ハロウィンがイノベーションでクリスマスはマーケティングの理由
では次に、ハロウィンがイノベーションでクリスマスはマーケティングとする理由について説明します。

(画像:poxabayより引用)
クリスマスは1922年頃に不二家がクリスマスケーキを販売して以降、ケーキ以外にも様々な関連商品が売られ、記念日文化研究所によると7000億円規模の市場となりました。2015年には1兆円に達したとされています。
まさに日本でクリスマスを祝い始めた当初はイノベーションと言えたでしょう。しかしビジネスとして見た場合、現在ではケーキのデザインに多少の変化や流行があるものの新しい何かを行うことはほぼなく、いかに前年との違いを作って利益につなげるかといったマーケティングの要素が大きいのです。

(画像:poxabayより引用)
対するハロウィンはここ数年で一気に定着した感があります。
日本におけるハロウィンは2017年で約1305億円の市場規模とされています。
これまでクリスマスに次ぐ2番手の記念日市場だったバレンタインが同規模になるのに50年を要したのに対し、ハロウィンはわずか20年ほどで肩を並べ、2016年にはバレンタインを抜きました。今年は選挙の影響で前年比3%ほど減少し、バレンタインの方が経済効果が高くなりそうです。
いずれにしても本来日本には無関係なお祭りを導入し、見事1つの行事としたのはまさしくイノベーションでしょう。
とは言え、いきなりハロウィンが日本に定着したわけではありません。
ここからは主題と少しズレますが、日本でハロウィンが一般化しつつある歴史や理由を掘り下げたいと思います。
日本でハロウィンが新たに定着した歴史と理由
私も調べてわかったのですが、実は40年以上前から少しずつ日本で広めようと活動されていました。
てっきり電通などの広告会社が流行らせたのかと思いましたが、発端はお菓子メーカーの「モロゾフ」が1976年にハロウィン商品を販売したことです。
これを受け森永製菓社長が会長を務めていた「全国菓子協会」が1981年から「ハロウィンキャンペーン」を開始します。そこにサンリオやソニープラザなどの玩具、雑貨、文具を扱う業界も参入し徐々に流れは拡大していきました。
その後1983年に大ヒットした映画「E.T.」の中にハロウィンが出たことで大衆への認知度も高まり、原宿キデイランドではハロウィンパレードが行われました。
更に1997年に今では日本最大級となった川崎ハロウィン(通称:カワハロ)のパレードと、東京ディズニーランドでハロウィンイベントが開催され、回を重ねるごとに参加者が増大し今日に至るというわけです。
日本で流行った理由は色々と言われますが、
- 仮装(コスプレ)による非日常性
- 老若男女が楽しめる多世代性
- パレードやパーティーによって起こる一体感
- 10月末で他に大きなイベントがない季節性
などが挙げられます。
この様に性別や年代にとらわれないイベントなため、仮装のための衣装はもちろん、飲食、グッズ、このパレードを見るために外国人が観光に訪れるなど、様々な業種でハロウィンに絡めた施策が行われています。ハロウィン風の和菓子が販売されていたりもしますね。
そう言えばダイソーでもハロウィン関連の商品が明らかに去年より増えていましたし、1ヶ月前にはもう取り扱っていました。
また、宝くじの「オータムジャンボ」も平成29年度は『ハロウィンジャンボ』に名称変更しました。
TBSでは「ハロウィン音楽祭2017」という番組が10月25日(水)よる7時から行われます。
発想次第でまだまだイノベーションの余地がありそうですね。
ただし、ごみ問題や渋谷のスクランブルでの騒音問題などトラブルや解決のための費用も少なくなく、ここら辺は今後本当に行事として続かせるための課題です。
ハロウィンの由来・起源について
ハロウィンとはキリスト教の祝日である11月1日の万聖節(ばんせいせつ。別名「諸聖人の日」)前夜の10月31日に行われる古代ケルト人の収穫祝いが起源とされています。
ケルト人にとって1年の終わりは10月31日であり、この日は死者の魂が蘇り、悪霊・黒猫を連れた魔女などがいたずらや悪さをするため、仲間だと思わせるために悪魔やゾンビなど、怖い・グロい仮装をするのがハロウィンの特徴です。
ちなみにカボチャが使われるのは元々は株(カブ)だったのが、アメリカにハロウィンが伝わった時に馴染みが薄いカブではなく手頃で且つ加工もしやすいカボチャが代用され、それが世界各地に広まったそうです。
カボチャのおばけとして知られるジャック・オー・ランタンも元々はカブのお化けだそうですよ。
北海道には「ろうそくもらい」という北のハロウィンと呼ばれる行事がある
私が札幌出身なので書きますが、北海道には「ろうそくもらい」と言って8月7日の七夕(一部地域は7月7日ではなく8月7日が七夕)に
「ローソク出ーせー出ーせーよー 出ーさーないとー かっちゃくぞー おーまーけーにー噛み付くぞー」
と歌いながら各家を回りローソクやお菓子をもらう行事がハロウィン以前からあります。
まとめ
今回は、見方を変えると新鮮な発見につながるということでこのお話を紹介しました。
マーケティングとイノベーション、どちらが優れているという訳ではありません。
ただ、物に溢れ不便を感じることが昔に比べ少なくなってきた現代ではマーケティングだけでは消費者の欲求を満たすことが難しくなってきています。
商品自体もそうですが、それを体験したこと、またそれによって起こる感情など『新たな価値』を感じさせることがイノベーションであり、これからの時代に求められるものではないでしょうか。
P.S. ハロウィンが嫌いだ、盛り上がっている人達が理解できない、そういう人もいるでしょう。しかし、そこで思考停止していては新たな発想は浮かびません。
「何故流行っているのか」「何が受けているのか」を分析し考えることが新たなビジネスチャンスのきっかけとなるかもしれません。
この記事のカテゴリー:「 マーケティング 」一覧
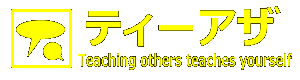


コメント