こんにちは。今回は【結婚式用のムービー(動画)を個人で作成する時の注意点】を、実際に仕事として依頼を受けて行ったことがある立場からご紹介します。
結婚式ではより良く演出するために、オープニングムービー・プロフィールムービー・エンディングムービーといった動画が使われますね。
業者にオーダーするとおしゃれな映像が期待できる反面、料金が高くなることも多いので、安いムービー作成業者を探したり知人に頼むことを考えたりすることもあるかと思います。
そこで、ムービーを自作(個人で作成)する場合の注意点をご紹介します。
結婚式のムービーを作成する時は5つのことに注意
私が作成した時に確認すべきと感じた注意点は次の5つです。
- 結婚式場のスクリーンのサイズを確認する
- 著作権や著作隣接権など、楽曲が利用可能かどうかを確認する
- 映像を流す方法(DVD/ブルーレイ)を確認する
- DVDを作成する時の注意点:一般的なプレーヤーで再生できる形式にする 他
- ムービー作成を依頼された場合:打ち合わせする内容を事前に確認する
順番に解説します。
結婚式場のスクリーンのサイズを確認する
下のイラストをご覧ください。
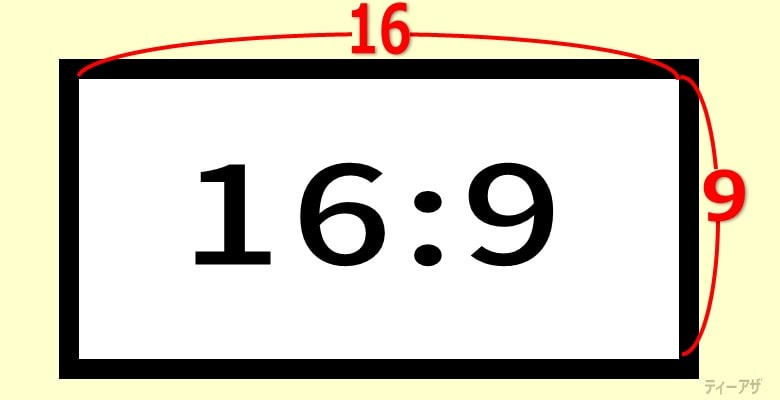
アスペクト比が16:9のスクリーンのイラスト
結婚式場で使われるプロジェクター用のスクリーンは「4:3」や「16:9」などサイズが会場ごとに異なります。
この「何対何」という画面の比率をアスペクト比と言います。
16:9は最近の主流で、パソコン向け YouTube の標準アスペクト比も16:9になっています。
しかし、会場によっては4:3の場合もまだまだあるので注意が必要です。
映像とスクリーンでアスペクト比が合わないムービーを作ってしまうとちゃんと上映されないので、事前に「スクリーンのアスペクト比を教えてください」と会場に確認しましょう。
著作権や著作隣接権など、楽曲が利用可能かどうかを確認する
結婚式・披露宴といえば、木村カエラさんの「Butterfly」やSuperflyさんの「愛をこめて花束を」など、定番の曲がありますね。
BGMで流したり余興で新郎新婦のご友人が歌ったりしますが、JASRACなどが権利を管理する楽曲の場合は注意が必要です。
法律が複雑なので簡単に説明すると、BGMとしてCDから曲を流す場合は「著作権」が、映像に曲を組み込む場合は更に「著作隣接権」が関わり、それぞれ使用料金が発生します。
特に、ムービーにデータとしてJ-POPなど権利が絡む楽曲を取り込む場合はISUM(=一般社団法人 音楽特定利用促進機構)に登録のある事業者でないと権利処理の手続きができません。
どうしても映像に合わせて上記のようなJ-POPを使用したい場合は、映像とCDを別にしてタイミングを合わせて曲をかけるなどであれば、式場がJASRACと包括契約をしてさえいれば可能です。
思わぬトラブルにならないよう、結婚式や披露宴に使う会場がJASRACやISUMと契約を結んでいるか事前に確認しましょう。
もっと詳しく知りたい方は「著作隣接権 ブライダル」などで検索すると良いです。
映像を流す方法(DVD/ブルーレイ)を確認する
2019年現在では、まだ式場の多くは映像を流すのにDVDを使用しています。
「張り切ってブルーレイで作成したのに結婚式で流せない」なんてことにならないよう、こちらも会場に確認しましょう。
DVDを作成する時の注意点:一般的なプレーヤーで再生できる形式にする 他
持ち込みムービーを自作する場合、やってしまいがちなのがこの再生の形式を失敗することです。
どういうことかというと、DVDを家庭用のプレーヤーなどで再生できるようにするには「DVDビデオ形式」や「DVD-VR形式」にファイルを変換しなければいけません。
この作業をオーサリングと言い、オーサリングソフトでないと「パソコン上やYouTubeにアップした時は再生できるのに、DVDプレーヤーだと再生できない」といったことが起こります。
例えばWindows7やVistaに入っている「Windows DVD メーカー」というオーサリングツール(ソフト)であれば、プレーヤーで再生できるDVDが作れます。
しかし、似たような名前の「ムービーメーカー」では作れません。
ムービーがちゃんと結婚式場のプレーヤーで再生できるか確認しましょう。
また映像を作成する時は、他にも注意しなければいけません。
せっかく再生できても次のようなことに気をつけないと、せっかくのムービーを作り直すことになります。
DVDの前後5秒くらいは空ける(黒画面を入れる)
これは式場で映像を流す時に途中から始まったり、ぶつ切りになったりするのを防ぐためです。
字幕を入れる時は句読点(「。」や「、」)を入れない
これは見やすさという観点以外にも、「区切る」など結婚式にふさわしくない意味合いがあるため、マナーとしても句読点を字幕では使わないようにしましょう。
字幕は画面端に寄せすぎない
字幕をあまり上下左右に寄せてしまうとプロジェクターによっては見切れてしまう可能性があります。
全体的に映像は少し中央に寄せておきましょう。
(基本的には)字幕は人物の顔に重ならないようにする
新郎新婦や親族、ご友人など、映像に写る顔に文字がかぶると失礼なので気をつけましょう。
ただし私は以前、「YouTubeによくあるまとめ風の動画のように、文字が上にスクロールするムービーにしてほしい」という依頼を受けたことがあるので、必ずしもこの限りではありません。
大事なのは新郎新婦が喜び、不快な思いをしないことだと思います。
ムービー作成を依頼された場合:打ち合わせする内容を事前に確認する
新郎新婦などにムービー作成を依頼された場合は打ち合わせの内容を事前に確認することを強く推奨します。
なぜなら私が最も時間がかかり苦戦したのがこの部分だからです。
作成を依頼する側は動画を作成するのにどれくらい労力がかかるかを知らないし考えません。
そのため、変更や修正を何度も依頼してきます。
例えば次のようなことがよくあります。
- エンディングムービーなどで流れる参加者(列席者)一覧について:
- 名前が違った
- 漢字を間違えた
- 順番を変更したい
- やっぱり違う写真を使ってほしい
- この部分はもう少し長く(または短く)映してほしい
要望に応えたい気持ちはあると思いますが、あれもこれも作成する側がやってしまうと、いつまで経っても作成が終わらないですし、報酬との割が合わなくなる場合もあります。
- 「変更は○回まで無料。それ以上は別料金」
- 「絶対に入れたい文面は事前にチェックしてから送ってもらう」
- どういうムービーにしたいかイメージを依頼する側と作成する側とでしっかりと共有する
など、打ち合わせする内容を事前に確認しましょう。
おさらいとまとめ
それではおさらいとまとめです。
結婚式のムービーを自作する時は次の点に気をつける
- 結婚式場のスクリーンサイズ(アスペクト比)
- 楽曲の著作権や著作隣接権など利用可能かどうか
- DVD、ブルーレイなど会場のプレーヤーにあったもので作成する
- DVDを作成する場合は一般的なプレーヤーで再生できるデータ形式にする
- ムービー作成を依頼された場合は依頼主との打ち合わせ内容を事前に確認する
結婚式以外にも送別会や卒団式など、ムービーを使う機会は色々ありますね。
特に近年ではAndroidやiPhoneといったスマホでもある程度の編集ができるためYouTubeなどへの投稿が簡単になり、動画を作成したい人や、ユーチューバーを目指して既に動画投稿している人も増えています。
しかし公的な場所で動画を公開する時は、今回ご紹介したような注意点がいくつかあるので気をつけましょう。
関連カテゴリー:動画・YouTube
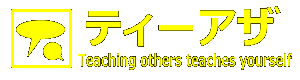

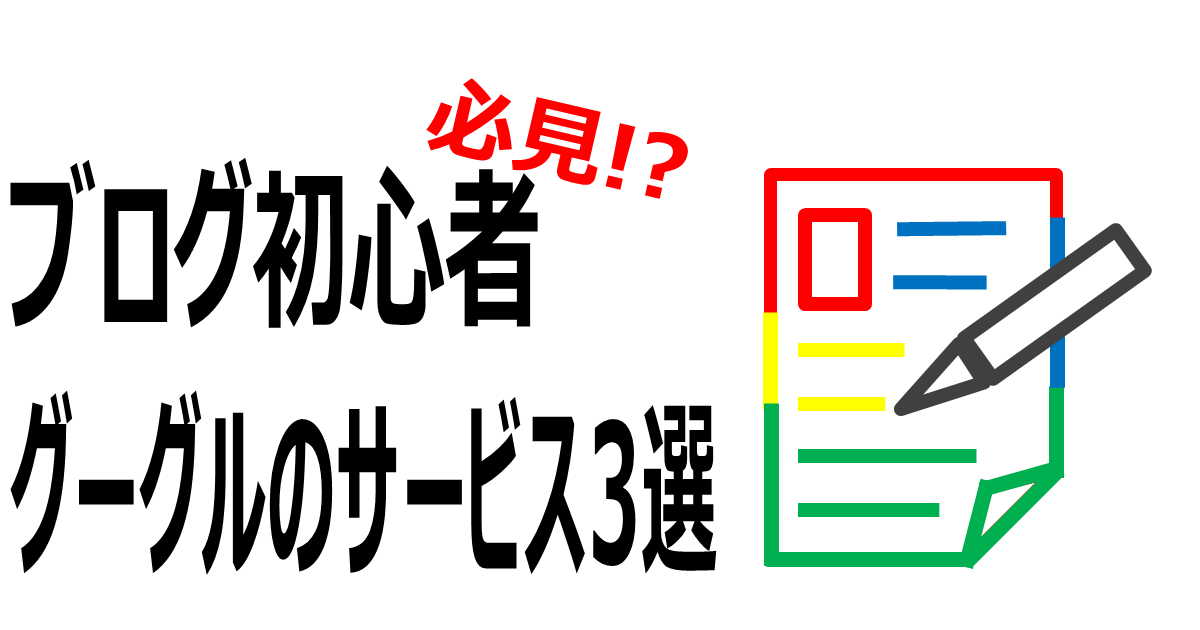
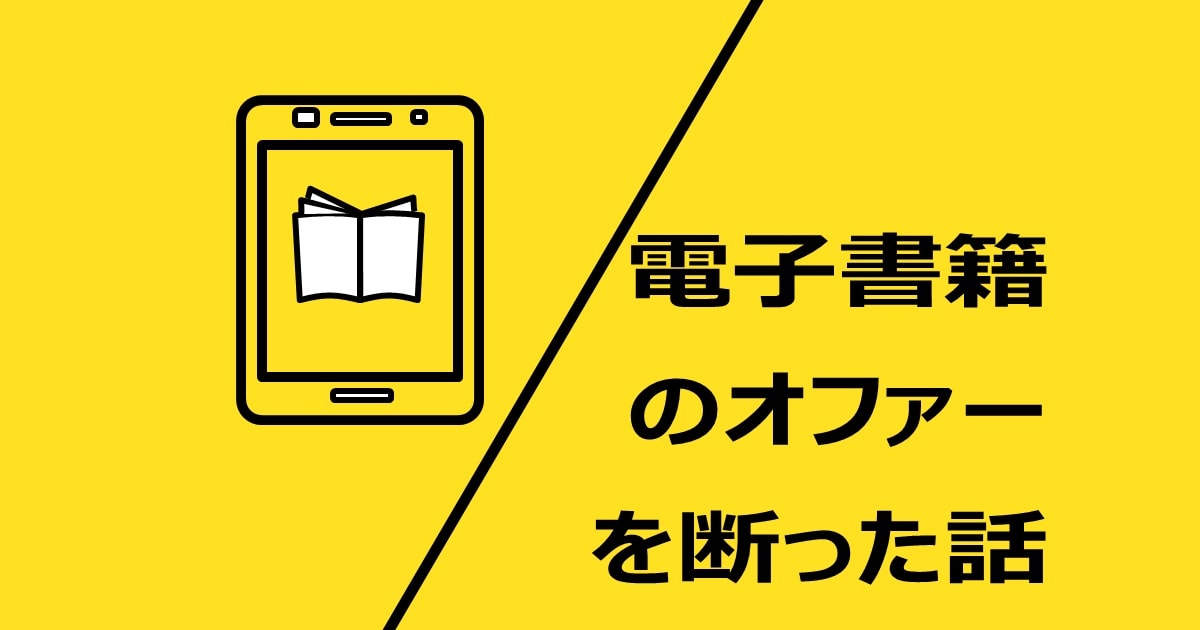
コメント